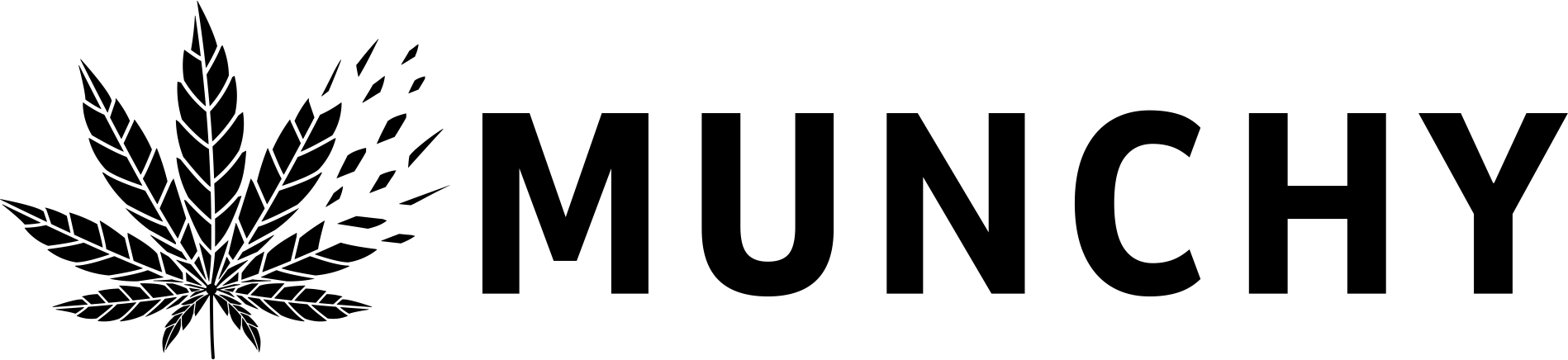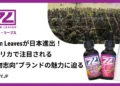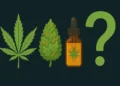ラオスは2022年12月に医療用・商用大麻の栽培、販売を解禁する合意を発布し、2023年1月から施行した。これはアジアでは初めてのことであり、大麻産業の可能性に注目が集まっている。本記事では、ラオスの大麻解禁の背景と内容、およびアジアで広がる大麻産業の現状と展望について紹介します。
ラオスの大麻解禁の背景と内容
ラオスはこれまで、産業用大麻の栽培や医療用大麻の使用を厳格に禁止してきた。しかし、近年、大麻に含まれるカンナビノイドと呼ばれる成分が医療や健康に有用な効果を持つことが科学的に明らかになり、欧米やカナダなどでは医療用大麻やレクリエーショナル(娯楽)用大麻の合法化が進んでいる。また、中国やタイなどでも産業用大麻や医療用大麻の規制緩和がおこなわれており、アジアでも大麻産業の発展が期待されている。
ラオス保健省は2018年11月、医療用大麻の使用解禁について政府に提案した。2021年11月にはカナダのカルティバとラオス保健省伝統薬研究所が共同で大麻の栽培や分析試験、商用抽出加工施設の建設に合意しており、現在建設が進められている。そして2022年12月28日付で、「医療用・商用大麻(Cannabis sativa L.)の管理に関する保健大臣合意(No.3789/MOH)」が発布され、2023年1月26日から施行された。
同合意では、これまで一切禁止してきた大麻の栽培、加工、保管、流通販売、輸出入を条件付きで認可した。具体的には以下のような内容となっている。
- カンナビジオール(CBD)を主成分とする医療用と商用の製品でのデルタ9-テトラヒドロカンナビノール(THC)含有基準は、乾燥重量の1%未満もしくは製品の0.2%未満と定めた。
- 製品ではTHCが0.2%未満、CBDはTHCの4倍以上含まれることを条件とした。
- 国内で大麻関連事業を行う企業は、保健省に技術者を登録する必要がある。技術者はラオス国籍の保有者かつ居住者で、薬学もしくは化学の学士以上の学歴と、5年以上の製薬の実務経験が求められる。
- 事業ライセンスは3年間で延長が可能。
- 大麻栽培で使用する品種は登録済みの種子に限定する。種子の輸入量は栽培面積1ヘクタール当たり5万2,000種子もしくは2.2キログラムまでとした。
- 加工では、大麻の部位により用途を定めており、種子は抽出により食品添加物、新薬、生薬、健康食品への利用、花序(複数の花が集団をなしているもの)は新薬、生薬、健康食品、食品添加物、飲料、化粧品への利用、葉は伝統薬、茶、化粧品への利用、根や茎、繊維は伝統薬、化粧品(洗浄用途)とした。
- 国内販売では、食品薬品局への登録が必要で、花序はTHC1%未満(乾燥重量)と規定した。健康食品や化粧品、飲料、CBDオイルは登録後に一般販売が可能とした。
なお、同合意では外資規制については不明瞭なことから、今後の通達を待つ必要がある。
アジアで広がる大麻産業の現状と展望
ラオスが大麻解禁に踏み切ったことで、アジアで広がる大麻産業に新たな動きが生まれそうだ。アジアではすでに中国やタイなどが産業用大麻や医療用大麻の規制緩和をおこなっており、市場規模や投資額も拡大している。
中国では2010年から産業用大麻の栽培を認めており、主に繊維や紙などの原料として利用されてきた。しかし近年ではCBDオイルなどの医療や健康関連製品への需要が高まっており、中国政府もCBD抽出や加工を許可する地域を拡大している。中国は世界最大のCBD生産国となっており、2020年には約7億ドル(約770億円)の市場規模に達したと推計されている。また中国企業は海外でも積極的に大麻事業に参入しており、カナダやオーストラリアなどで栽培や販売をおこなっている。
タイでは2018年12月に医療用大麻の合法化を決めた。これはアジアでは初めてのことであり、タイ政府は医療用大麻を国家戦略と位置付けている。タイでは2020年8月から医療機関や伝統医学院などで医療用大麻製品の処方が開始された。また2021年2月には一般市民も自宅で6本までの大麻草を栽培することが認められた。さらに2022年6月には禁止薬物のリストから大麻を除外し、20歳以上であれば誰でも大麻を栽培できるようにした。タイでは観光立国として欧米からの観光客を呼び込むためにも、大麻解禁に積極的だと見られている。
これらの国々は、大麻産業が経済成長や雇用創出、農村振興などに貢献すると期待している。また、医療や健康面でも、大麻に含まれるカンナビノイドが慢性痛やてんかん、不安障害などの治療に効果的だというエビデンスが増えてきており、多くの患者や医師が利用を求めている。さらに、薬物政策の見直しも一つの要因となっている。従来の薬物取り締まりは、薬物使用者を刑罰化することで社会的排除や人権侵害を招き、薬物問題の解決には逆効果だという批判が高まっている。そのため、薬物使用者に対しては教育や支援を提供し、薬物の危険性やリスクを減らす「ハームリダクション」のアプローチが注目されている。
一方で、大麻解禁には様々な課題やリスクも伴う。まず、国連条約に反していることは変わらない。国際社会との摩擦や制裁の可能性も否定できない。また、大麻は依然として薬物であり、乱用や過剰摂取による健康被害や社会問題を引き起こす恐れもある。特に若年層や精神的に不安定な人々は大麻の影響を受けやすく、精神疾患や学業不振、交通事故などのリスクが高まるという研究もある。さらに、大麻産業は巨大な利益を生むため、不正や汚職、暴力などの犯罪行為も発生する可能性がある。特にアジアでは法整備や規制体制が十分ではない場合が多く、適切な管理や監督が必要となる。
まとめ
ラオスが医療用・商用大麻の栽培・販売を解禁したことで、アジアで広がる大麻産業に新たな動きが生まれそうだ。アジアではすでに中国やタイなどが産業用大麻や医療用大麻の規制緩和をおこなっており、市場規模や投資額も拡大している。大麻産業は経済成長や医療改善、薬物政策の転換などの効果をもたらす可能性があるが、同時に国際法違反や健康被害、社会問題などの課題やリスクも伴う。アジア各国は大麻解禁のメリットとデメリットを慎重に検討し、適切な管理や監督をおこなう必要があるだろう。