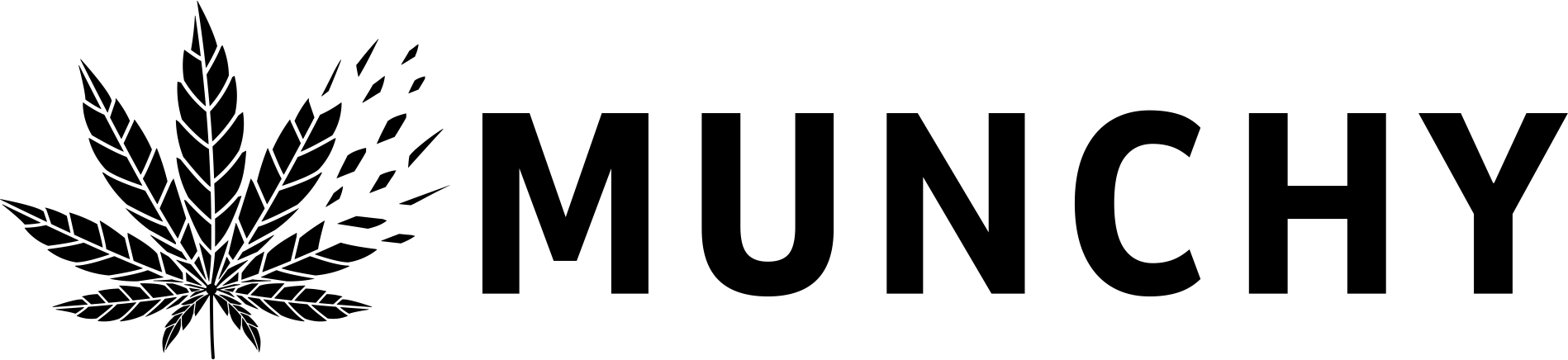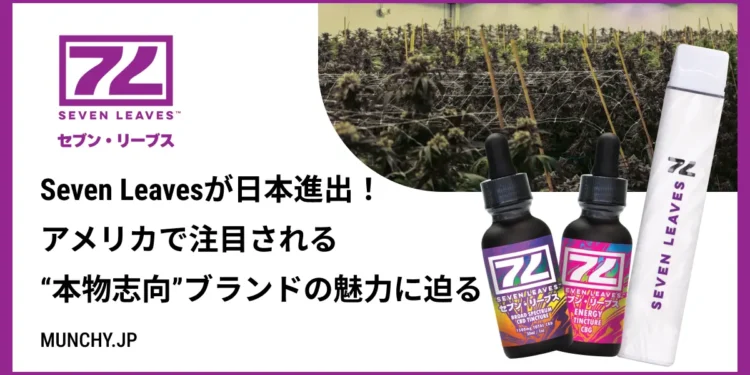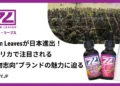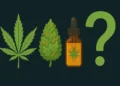日本では、大麻の所持や栽培などが自己使用目的であっても重い刑罰(所持は5年以下、栽培は7年以下の懲役)が予定されていますが、大麻の使用それ自体を処罰する条文はありません。しかし、近年、若者を中心に大麻の乱用が増加しているという懸念から、厚生労働省の専門家会議が「大麻使用罪」という新たな条文を作ることの是非を検討しています。
大麻使用罪とは何か?
日本では、大麻の所持や栽培などが自己使用目的であっても重い刑罰(所持は5年以下、栽培は7年以下の懲役)が予定されていますが、大麻の使用それ自体を処罰する条文はありません。しかし、近年、若者を中心に大麻の乱用が増加しているという懸念から、厚生労働省の専門家会議が「大麻使用罪」という新たな条文を作ることの是非を検討しています。
大麻使用罪とは、大麻を吸引したり飲食したりすることを犯罪とする法律です。具体的な法定刑はまだ決まっていませんが、おそらく所持罪と同じく最高で5年くらいの懲役になる可能性があると思われます(ヘロインや覚醒剤の自己使用は10年以下の懲役)。
このように、大麻使用罪が制定されれば、それまで適法だった行為が特定の日以降犯罪になるわけです。過去にも、児童買春児童ポルノ禁止法や不正アクセス禁止法などがそうでした。法の制定と施行は事前に予告されますので、ある日突然逮捕ということはもちろんありませんが、それまで普通に行っていた行為に朝起きてみれば深い穴が開いていたようなもので、その日から細心の注意をしないといけないという場合もあります。
大麻使用罪の必要性と問題点
では、なぜ大麻使用罪が必要なのでしょうか?その主な理由は以下の2つです。
- 大麻使用が社会的な問題となっている
- 大麻使用が他の薬物乱用につながる
一方で、大麻使用罪には以下のような問題点も指摘されています。
- 大麻使用の害悪性や危険性について科学的な根拠が不十分
- 大麻使用者に対する支援や治療よりも刑罰や排除を優先することになる
- 大麻使用者に対する偏見や差別を助長することになる
- 大麻使用者に対する人権侵害やプライバシー侵害が増えることになる
これらの理由や問題点について、詳しく見ていきましょう。
大麻使用が社会的な問題となっている
大麻使用罪の必要性を主張する側は、大麻使用が社会的な問題となっているという事実を根拠にしています。実際に、警察庁の統計によると、2020年に大麻に関連した事件が摘発された人数は5,273人で、過去最高を更新しました。そのうち、30歳未満の人が65%を占めており、若者の大麻乱用が深刻化していることがわかります。
また、インターネットやSNSの普及によって、大麻の入手や情報交換が容易になっていることも問題視されています。特に、海外で合法化や規制緩和が進んでいることや、芸能人や有名人が大麻使用を公言したり擁護したりすることが、若者の間で大麻に対する誤った認識や興味を生んでいるという指摘もあります。
このように、大麻使用罪の必要性を主張する側は、大麻使用が社会的な問題となっていることをもとに、大麻使用者に対する抑止力や教育効果を高めるためには刑罰が必要だという立場をとっています。
大麻使用が他の薬物乱用につながる
もう一つの理由は、大麻使用が他の薬物乱用につながるということです。これは、「ゲートウェイ理論」と呼ばれる仮説で、大麻のような比較的軽度な薬物から始まって、次第により強力で危険な薬物へと移行していくというものです。
この理論は、大麻使用者の中にはヘロインや覚醒剤などの重度な薬物乱用者になる人もいるという統計的な関係性や、大麻使用が脳内の報酬系を刺激して依存性や耐性を高めることで他の薬物への欲求を増幅させるという生理学的なメカニズムに基づいています。
このように、大麻使用罪の必要性を主張する側は、大麻使用が他の薬物乱用につながる可能性があることをもとに、大麻使用者に対する早期発見や介入を行うためには刑罰が必要だという立場をとっています。
大麻使用の害悪性や危険性について科学的な根拠が不十分
一方で、大麻使用罪の問題点を指摘する側は、大麻使用の害悪性や危険性について科学的な根拠が不十分だということを主張しています。実際に、大麻使用の影響に関する研究はまだ十分ではなく、その結果も一様ではありません。
たとえば、大麻使用が精神疾患や認知障害を引き起こすという主張は、多くの研究によって示されているが、因果関係は明確ではなく、大麻使用と精神疾患の発症には個人差や遺伝的要因なども関係している可能性がある1。また、大麻使用が認知障害や学習障害を引き起こすという主張も、大麻使用の量や頻度、開始年齢、使用期間などによって影響が異なることや、大麻使用以外の要因(例えば、社会経済的背景や教育水準など)も考慮しなければならないことが指摘されています。
さらに、大麻使用が他の薬物乱用につながるというゲートウェイ理論についても、科学的な証拠は不十分であり、議論の余地があるとされています。ゲートウェイ理論は、統計的な相関関係を示すだけで、因果関係を示すものではありません。また、大麻使用と他の薬物乱用の間には、個人的な嗜好や傾向、社会的な環境や影響、法的な可用性などが関与している可能性があります。したがって、大麻使用罪の問題点を指摘する側は、大麻使用の害悪性や危険性について科学的な根拠が不十分だということをもとに、大麻使用者に対する刑罰は不当であり、効果も疑わしいという立場をとっています。
大麻使用者に対する支援や治療よりも刑罰や排除を優先することになる
もう一つの問題点は、大麻使用者に対する支援や治療よりも刑罰や排除を優先することになるということです。これは、「刑事化」と呼ばれる現象で、大麻使用者が犯罪者として扱われることで、社会から孤立したり差別されたりすることで、さらに薬物乱用の悪循環に陥る可能性があるというものです。
この現象は、大麻使用者が自ら支援や治療を求めることを妨げたり、支援や治療を受けたくても受けられなかったりすることで起こります。例えば、大麻使用者が自ら支援や治療を求めることを妨げる要因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 大麻使用者自身が自分の行為に問題意識を持たないか低い
- 大麻使用者自身が自分の行為に対する刑罰や社会的な制裁を恐れる
- 大麻使用者自身が自分の行為に対する支援や治療の必要性や効果を疑う
このように、大麻使用罪の問題点を指摘する側は、大麻使用者に対する支援や治療よりも刑罰や排除を優先することになるということをもとに、大麻使用者に対する刑罰は効果がなく、かえって悪影響を及ぼすという立場をとっています。
大麻使用者に対する偏見や差別を助長することになる
さらに、大麻使用者に対する偏見や差別を助長することになるという問題点も指摘されています。これは、「スティグマ」と呼ばれる現象で、大麻使用者が社会的に否定的なレッテルを貼られることで、自己イメージの低下や自己効力感の喪失、自尊心の減少などの心理的苦痛を経験することで、さらに薬物乱用の悪循環に陥る可能性があるというものです。
この現象は、大麻使用者が社会から受けるスティグマ(外的スティグマ)と、大麻使用者が自分自身に抱くスティグマ(内的スティグマ)の両方で起こります。例えば、大麻使用者が社会から受けるスティグマ(外的スティグマ)としては、以下のようなものが挙げられます。
- 大麻使用者が法律や道徳に反した人間だと見なされる
- 大麻使用者が危険かつ不安定な人間だと見なされる
- 大麻使用者が無能かつ無責任な人間だと見なされる
また、大麻使用者が自分自身に抱くスティグマ(内的スティグマ)としては、以下のようなものが挙げられます。
- 大麻使用者が自分の行為に対して罪悪感や恥辱感を感じる
- 大麻使用者が自分の行為に対して否定的な評価や期待を内面化する
- 大麻使用者が自分の行為に対して変化や改善が不可能だと諦める
大麻使用罪の国際的な比較
大麻使用罪の有無や罰則の厳格さについて、日本と他の国々との比較をしてみましょう。日本は、大麻使用罪を設けていないが、大麻所持罪に対しては最高で懲役5年以下の刑を規定しており、大麻栽培罪や大麻譲渡罪に対しては最高で懲役7年以下の刑を規定している。これらの罰則は、国際的に見ても厳しいです。
一方、欧米やオセアニアなどの先進国では、近年、大麻の医療用途や嗜好用途に対する規制緩和や合法化の動きが広がっています。例えば、カナダでは2018年に大麻の嗜好用途を合法化し、成人が一定量の大麻を所持したり栽培したりすることを認めたほか、オランダでは1976年以来、大麻の所持や使用を非刑事化し、コーヒーショップでの販売や消費を容認している。また、アメリカでは連邦法では大麻は違法なままだが、州レベルでは医療用途や嗜好用途に対する合法化や非刑事化が進んでおり、現在では18州と首都ワシントンD.C.で嗜好用途が合法化されている。
これらの国々では、大麻使用罪を設けていないか、あっても軽微な罰則にとどめており、大麻所持罪や大麻栽培罪に対しても日本よりも緩やかな刑罰を規定している場合が多い。例えば、カナダでは成人が30グラム以下の乾燥した大麻またはその同等量を所持することは合法であり、それを超える場合でも最高で罰金5000カナダドル(約45万円)以下又は懲役6か月以下となっている。オランダでは成人が5グラム以下の大麻を所持することは違法だが起訴猶予とされ、それを超える場合でも最高で罰金8100ユーロ(約110万円)以下又は懲役1年以下となっている。アメリカでは州によって異なるが、例えばカリフォルニア州では成人が28.5グラム以下の乾燥した大麻またはその同等量を所持することは合法であり、それを超える場合でも最高で罰金100ドル(約1万円)以下となっている。
これらの国々では、大麻使用者に対する刑罰よりも支援や治療を優先する方針をとっており、大麻使用者の人権や尊厳を尊重し、社会的な排除や差別を防ぐことを目的としています。また、大麻の合法化や規制緩和によって、大麻の品質や安全性を確保し、大麻の不正取引や密売による犯罪や暴力を減らし、大麻に関する税収や雇用を増やすことを狙っている。さらに、大麻の使用に関する科学的な知見やデータの収集・分析を行い、大麻の有害性や依存性についての啓発や教育を強化することで、大麻使用者の健康や福祉を向上させることを目指している。
以上のように、日本と他の国々とでは、大麻使用罪の有無や罰則の厳格さについて大きな違いがあります。これは、各国が大麻に対する歴史的・文化的な背景や社会的な認識、法的な立場や方針などに基づいて、それぞれの国情に応じた規制体制を構築してきた結果であると言えるでしょう。日本は、大麻使用罪を設けていないが、大麻所持罪などに対しては厳しい刑罰を規定し、大麻使用者に対する刑事責任を重く問うことで、大麻乱用の未然防止と撲滅を目指している。他の国々は、大麻使用罪を設けていないか軽微な罰則にとどめており、大麻使用者に対する支援や治療を優先することで、大麻使用者の人権や尊厳を尊重し、社会的な排除や差別を防ぐことを目指しています。このような違いは、各国が抱える薬物問題の性質や規模、薬物政策の目標や効果などにも影響しており、今後も注視していく必要があるでしょう。
まとめ
本記事では、日本における大麻使用罪の現状や今後について解説していきました。
日本政府は嗜好用大麻を合法化する意見を聞かない状況にあると言えるでしょう。
今後の動きに注目も必要ですが、日本でTHCが合法になるのはまだ時間がかかりそうです。